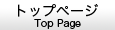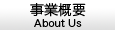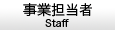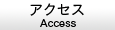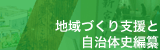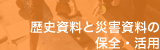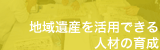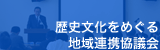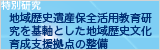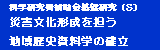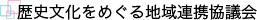 |
第12回 地域歴史遺産の可能性を考える
- 2014年2月2日(日)11:00〜17:00
- 人文学研究科B331教室/交流会場:B333教室、B334教室(文学部B棟3F)
- 主催 神戸大学大学院人文学研究科、同地域連携センター
- 共催 兵庫県教育委員会、科学研究費補助金基盤研究(S)「大規模自然災害時の史料保全論を基礎とした地域歴史資料学の構築」研究グループ
- 後援 淡路市教育委員会
現在、さまざまな分野で、大学と地域社会との関係が希薄になり、大学で蓄積されてきた知的資源や学術的な専門性が社会からの要請に応えられていないという指摘がされています。そうした指摘があるなか、人文学研究科地域連携センターは、この12年間、大学と地域社会を結ぶべくさまざまな試行錯誤と努力を重ねてきました。それを通じてみえてきた点の一つは、歴史資料の分析によって得られた学術的成果や知識を、専門領域だけに閉じ込めることなく、地域社会の人々がもつ知的欲求や関心に結びつけ、両者間のコミュニケーションを豊かにする事の重要性です。
歴史資料を通じた大学と地域社会の結び方は単純ではありません。自治体や地域リーダーのはたす役割の有無などによって多様な形をとりますが、その中には共通する成果と課題があるように思います。こうした点を私たちは、今年度の7月に発刊された『「地域歴史遺産」の可能性』(岩田書院)にまとめました。
内容は多岐にわたっていますが、歴史遺産を活かしたまちづくり事業を前進させるためには、これに対して関係者からご意見を賜るとともに、なによりも相互に課題を共有し議論することが重要だと考えます。
そこで、今年度の協議会のテーマを、「地域歴史遺産の可能性を考える」とします。地域歴史遺産というものが、どのような広がりをもち、それをめぐる人々の関係や、それを支える環境の構築がどうあるべきかなどについて、活発な議論をしたいと思います。
第1部は、近年新たな成果をあげている諸団体の活動報告を通して、関係者同士の交流と相互議論を深める場とします。第2部は、これまでの大学の取り組みについて報告し、その成果や課題について関係者から意見をいただき、今後の地域歴史遺産の保全・活用の意義やその可能性を考えたいと思います。
本年度も協議会の間に時間をとり、各団体の方々が交流できるコーナーやポスターセッションの場を設けます。多くの方々に活動の成果物や書籍等をお持ちよりいただき、展示・交流していただければ幸いです。ご参加をお待ちします。
プログラム
| 11:00 主催者挨拶(内田一徳・理事副学長/藤井勝・地域連携センター長) 11:10〜11:20 趣旨説明(奥村弘・神戸大学地域連携推進室室長) 第Ⅰ部 活動報告・交流会 11:20〜11:35 活動報告(1) 海部 伸雄氏(淡路市文化財保護審議会副会長) 「淡路島における歴史資料の現状と課題 〜活用の試みを中心に〜(仮)」 11:35〜11:50 活動報告(2) 國重 和義氏(神戸大学近世地域史研究会) 「覩聞記の研究と刊行をめぐって(仮)」 11:50〜12:05 活動報告(3) 藤尾 昇氏(香寺歴史研究会会員) 「岩部地区の大字誌の作成をめぐって(仮)」 12:05〜12:20 質疑応答 12:20〜13:20 昼食・交流会 第Ⅱ部 地域歴史遺産の可能性を考える 13:20〜13:50 報告(1) 市澤 哲(神戸大学) 「地域のなかで大学がはたす役割(仮)」 13:50〜14:10 報告(2) 坂江 渉(神戸大学) 「自治体職員との信頼・連携関係の構築(仮)」 14:10〜14:30 報告(3) 木村 修二(神戸大学) 「神戸市灘区との連携事業について(仮)」 関連コメント 伊藤 浄真氏(摩耶山天上寺副住職・宗務長) 「地域から大学に期待するもの(仮)」 14:30〜14:50 報告(4) 河島 真(神戸大学) 「地域と共に生きる高校教師(仮)」 14:50〜15:10 休憩・交流会 15:10〜15:30 コメント(1) 竹見 聖司氏(篠山市政策部企画課室長) 15:30〜16:00 コメント(2) 遠州 尋美氏(大阪経済大学経済学部教授・工学博士) 16:00〜17:15 総合討論 司会:奥村弘、村井良介(神戸大学) 17:30〜19:00 懇親会 |
協議会の記録
この協議会の内容については、神戸大学学術成果リポジトリKernel掲載の報告書をご覧ください。