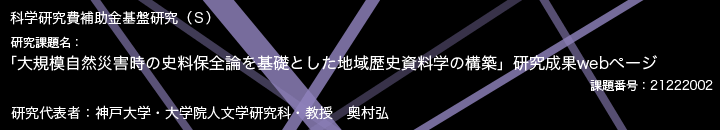
| English |

| 2013.9.11更新 |
■平成25年度・災害資料フォーラム
「阪神・淡路大震災から東日本大震災へ」
【日時】:2013年10月20日(日) 13:00~17:30
【会場】:神戸大学瀧川記念学術交流会館(神戸市灘区六甲台町1-1)
http://www.kobe-u.ac.jp/guid/access/rokko/rokkodai-dai2.html (ローカルマップ内の54です)
※参加無料
【趣旨】
東日本大震災の被災地では、震災に関する写真や映像などのデジタルデータ収集とその
デジタルアーカイブの構築が、国内外において積極的に進められている。それとともに、
災害とその復旧・復興を総体としてとらえ、被災地に生きる人びとの様々の経験や営み
をとどめていくためには、現物の災害資料を収集・保存し、後世に引き継いでいくこと
もまた重要である。
東日本大震災のアーカイブへの高い関心が示すように、阪神・淡路大震災以降、自然災害が
頻発する日本社会において、災害を記録し伝えていくことの重要性は社会的な広がりをもっ
て認識されてきている。
このシンポジウムでは、阪神・淡路大震災以降の国内外における災害資料の収集・活用の
事例を学ぶとともに、日本社会の中において災害資料のもつ意義を国際的・研究的な視点
からとらえ、いかにして災害の記憶を継承し、災害文化を形成していくのかについて考える。
【プログラム】
<趣旨説明>
・奥村弘(神戸大学人文学研究科)
<報告>
・佐々木和子氏(神戸大学地域連携推進室)
「資料をのこす―阪神・淡路大震災の経験から」
・リズ・マリ氏(人と防災未来センター研究部)
「災害研究とアーカイブ―1906 年サンフランシスコ大地震を事例として」
・吉野高光氏(双葉町教育委員会)
白井哲哉氏(筑波大学図書館情報メディア研究科)
「双葉町役場埼玉支所における東日本大震災関係資料の保全作業について」
・柴山明寛氏(東北大学災害科学国際研究所)
「東北大学「みちのく震録伝」の取り組みと宮城県内の震災アーカイブについて」
・池田勝彦氏(国立国会図書館)
「国立国会図書館東日本大震災アーカイブの取り組みについて」
<コメント>
・塩崎賢明氏(立命館大学政策科学部)
・本間宏氏(福島県文化振興財団)
・矢田俊文氏(新潟大学人文学部)
<パネルディスカッション>
【懇親会】
時間:18:00~20:00
会場:神戸大学瀧川記念学術交流会館1階
※懇親会に参加希望の方は、ご所属・お名前を明記の上
10月15日(火)までに下記までご連絡ください。
【懇親会申込先】
神戸大学人文学研究科・吉川圭太
E-mail : yoshik*port.kobe-u.ac.jp(*を@に変えてください)
【主催】:科学研究費補助金基盤研究(S)「大規模自然災害時の史料保全論を基礎とした地域歴史資料学の構築」研究グループ
【共催】:神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター
神戸大学震災復興支援・災害科学研究推進室
阪神・淡路大震災資料の保存・活用に関する研究会
※チラシ(PDF)はこちらです
■平成24年度・被災地フォーラムⅡin岡山
「大規模自然災害に備える―災害に強い地域歴史文化をつくるために―」
・日時:2013年3月2日(土) 14時~17時30分
・場所:岡山大学文化科学系総合研究棟2階・共同演習室
(岡山市北区津島中3丁目1-1/津島北キャンパス)
・趣旨:
東日本大震災以降、被災地の個人や地域の歴史文化を未来につなぎ、崩壊の危機を
むかえた地域社会の再生のために、あらためて地域歴史資料が注目されている。こうした
地域歴史資料を自然災害から守るために、私たちは災害発生時にどのような対応をすれ
ばよいのだろうか。また、災害に備えて日常から資料保全をめぐってどのような準備を進め
ればよいのか、あらためて考える時がきている。
阪神・淡路大震災以降、隔年規模で起こる大規模な地震や風水害の被災地域で、災害
から地域歴史資料を救出保全する資料保全団体が生まれ、各地で資料保全の取り組みが
展開されてきている。
こうした全国的な動きのなか、災害時における地域歴史資料の滅失を「予防」するため
には、「災害後の資料保全から、災害前の防災対策」が重要であることが、社会的な広がり
のなかで認識されてきた。2005年には、災害発生以前に予防的観点から歴史資料保全を
進める団体として岡山史料ネットが結成され、その後も山形や福島などで同様の「予防ネット」
が設立されてきている。
東日本大震災では、災害時の歴史資料保全のあり方とともに、災害に備えた「予防」の
重要性があらためて問い直された。この大震災をきっかけに、神奈川・和歌山・徳島などでも
予防ネットが設立されるなど、地域歴史資料をめぐる「予防」に向けた動きがより大きくなって
きている。
本フォーラムでは、災害前の歴史資料防災の取り組みを先進的に進めてきた岡山や大分
などの事例から学び、今後予想される大規模・広域災害に備えて効果的に歴史資料を保全
しうる予防のあり方について議論を深めたい。それを通して、災害に強い地域の歴史文化を
形成し、豊かにしていくために私たちは何ができるのかについて考えたい。
・プログラム:
<基調講演>
・倉地克直(岡山大学) 「「身の丈」の歴史学-記憶・記念物・拠点-」
<報告>
・定兼学(岡山県立記録資料館) 「模索する岡山県地域」
・首藤ゆきえ(井原市文化財センター)「自治体史編さん後の資料保存活動について」
・村上博秋(大分県立先哲史料館) 「防災的観点からみた「大分県記録史料調査事業」」
・新和宏(国立歴史民俗博物館) 「東日本大震災が我々に投げかけた課題
-千葉の資料ネットの取り組みと、課せられた使命-」
<コメント>平川新(東北大学)・矢田俊文(新潟大学)
<パネルディスカッション>
コーディネーター:奥村弘(神戸大学)・今津勝紀(岡山大学)
・主催:
岡山大学文学部
岡山史料ネット
基盤研究(S)「大規模自然災害時の史料保全論を基礎とした地域歴史資料学の構築」(被災地フォーラム)
・共催:
岡山県立記録資料館
岡山地方史研究会
岡山近代史研究会
※チラシ(PDF)はこちらです
■平成24年度・被災地フォーラム
「新潟県中越地震から東日本大震災へ―被災歴史資料の保全・活用の新しい方法をさぐる―」
・日時:2012年11月10日(土)・11日(日)
【11月10日(土)】
・場所:新潟大学総合教育棟D棟1階 大会議室(新潟大学五十嵐キャンパス)
http://www.niigata-u.ac.jp/top/access_ikarashi.html
・スケジュール:
第1部 13:00~14:45
「新潟県の大規模自然災害と資料保全の取り組み―新潟県中越地震から東日本大震災へ」
〔趣旨説明〕
〔報告〕
・奥村弘氏(神戸大学)
「新潟の取り組みに学ぶ―『災害・復興と資料』1号を読む―」
〔パネルディスカッション〕
パネラー:
・小林貴宏氏(山形文化遺産防災ネットワーク)
・森行人氏(新潟市歴史博物館)
・大楽和正氏(新潟県立歴史博物館)
・飯島康夫氏(新潟大学災害・復興科学研究所)
・齋藤瑞穂氏(新潟大学人文学部)
・田中洋史氏(長岡市立中央図書館文書資料室)
・奥村弘氏(神戸大学)
司会:
・矢田俊文氏(新潟大学災害・復興科学研究所)
第2部 15:00~17:50
「減災と復興にむけた現代的課題をさぐる」
〔報告〕
・田中洋史氏(長岡市立中央図書館文書資料室)
「新潟県中越地震と山古志村史編集資料」
・小林准士氏(島根大学法文学部)
「山陰地方の過疎における史料保存の課題」
・松下正和氏(近大姫路大学教育学部)
「二〇〇九年台風9号被災資料の保全と活用
―佐用郡地域史研究会・佐用町教育委員との連携―」
・多仁照廣氏(敦賀短期大学地域総合科学科)
「福井水害救出から見えた史料の社会的喪失」
・蛯名裕一氏(東北大学災害科学国際研究所)
「宮城県栗原市における歴史資料保全活動―二度の震災をうけて―」
・白水智氏(中央学院大学法学部)
「長野県栄村における文化財保全活動のこれまでと今後の課題」
・青木睦氏(国文学研究資料館)
「岩手県の震災被害と歴史資料―文化財レスキューの現場から―」
〔パネルディスカッション〕
パネラー:報告者
司会:矢田俊文・奥村弘
【11月11日(日)】
・被災地巡検
山古志→新潟県立歴史博物館→長岡震災アーカイブセンターきおくみらい(予定)
・主催:
新潟大学災害・復興科学研究所危機管理・災害復興分野
科学研究費補助金基盤研究(S)
「大規模自然災害時の史料保全論を基礎とした地域歴史資料学の構築」
〔研究代表者:奥村弘〕研究グループ
・共催:
新潟大学人文学部附置地域文化連携センター
新潟歴史資料ネットワーク
新潟史学会
■第14回地域歴史資料学研究会+第12回阪神・淡路大震災資料の保存・活用に関する研究会(共催)
・日時:2012年7月2日(月) 15:00~17:00
・場所:神戸大学大学院人文学研究科A棟1F・学生ホール
・報告
板垣 貴志氏(神戸大学大学院人文学研究科)
「書評『阪神・淡路大震災における住まいの再建―論説と資料―』(人と防災未来センター資料室、2012)」
石原 凌河氏(人と防災未来センター資料室)
「書評『伊丹からの発信 本文編』(伊丹市立博物館、2012)」
【ご案内】
東日本大震災から1年が経ちました。被災地だけでなく国内外においてひろく東日本大震災に関わる写真・映像
などの資料の収集・保存などのプロジェクトが進められています。
また昨年度末、地震発生から17年経った阪神・淡路大震災の被災地では、相次いで震災資料に関する資料集
などが出版されました。
つきましては、これらの出版物の検討を通じて、震災資料の収集・保存・公開・活用における現状と課題を
みなさまと議論できればと考えています。ご参加をお待ちしております。
・主催:
神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター
阪神・淡路大震災資料の保存・活用に関する研究会
科学研究費補助金基盤研究(S)「大規模自然災害時の史料保全論を基礎とした地域歴史資料学の構築」〔研究代表者:奥村弘〕研究グループ
震災復興支援・災害科学研究推進活動サポート経費(奥村弘)「災害資料学の実践的研究―阪神・淡路大震災の知見を基礎として―」
■第13回地域歴史資料学研究会
「水損資料救済取り扱いワークショップ」
・日時:2012年6月16日(土)~17日(日)
・場所:敦賀短期大学
【6月16日(土)】 13:00~17:30 ワークショップ
・挨拶:奥村弘氏(神戸大学)
・報告・ワークショップ
内田俊秀氏(京都造形芸術大学)
○和紙解説
○移動式凍結真空乾燥器の説明
松下正和氏(近大姫路大学教育学部)
◯汚損資料の洗浄(一紙もの)と吸水乾燥・送風乾燥
◯汚損資料の洗浄(帳面)とスクウェルチパッキング
多仁照廣氏(敦賀短期大学)
○水損資料の脱水
○資料の修復(固着展開、漉き嵌め、整形、綴じ)
【6月17日(日)】9:30~15:00 オプショナル・ワークショップ
・ワークショップ
多仁式漉き嵌め体験(講師:多仁照廣氏)
・主催:
科学研究費補助金基盤研究(S)「大規模自然災害時の史料保全論を基礎とした地域歴史資料学の構築」〔研究代表者:奥村弘〕研究グループ
福井史料ネットワーク
敦賀短期大学
■第12回地域歴史資料学研究会
・日時:2012年6月14日(木)16:00~18:00
・場所:神戸大学大学院人文学研究科A棟1F・学生ホール
・報告:
三村 昌司氏 (東京未来大学講師)
「地域歴史資料の活用と歴史学」
【ご案内】
近年、地域社会の急激な構造転換の中で、日本の地域社会で維持されてきた膨大な地域歴史資料は滅失の危機にある。
加えて、2011年3月11日に発生した東日本大震災以降、この危機は現在進行形でいっそう進むこととなった。
本科研では、このような状況にある地域歴史資料の保全・修復・活用についてのさまざまな研究を積み重ねてきた。
そのなかで、地
域歴史資料を、保全・修復することはもちろん、加えてそれをどのように活用していくかという問題と併せて
考察されるべき対象と位置づけてきた。
そこで今回の研究会では、とくに「活用」に主な焦点をあて、地域歴史資料を次世代に引き継ぎ、地域住民の歴史認識を
豊かにしう
る地域歴史資料学を構築する一助としたい。
・主催:
科学研究費補助金基盤研究(S)
「大規模自然災害時の史料保全論を基礎とした地域歴史資料学の構築」
〔研究代表者:奥村弘〕研究グループ
| 2012.1.19更新 |
■平成23年度総括研究会
・日時:2012年3月9日(金)午前10時30分~
・場所:神戸大学大学院人文学研究科
・主催:
科学研究費補助金基盤研究(S)
「大規模自然災害時の史料保全論を基礎とした地域歴史資料学の構築」
〔研究代表者:奥村弘〕研究グループ
| 2011.10.28更新、11.17更新 |
■平成23年度・被災地フォーラム
「東日本大震災における歴史資料保全活動をふまえた地域歴史資料学の中間提示をめざして」
・日時:2011年11月26日(土)・27日(日)
【11月26日(土)】
・場所:秋保の郷ばんじ家 会議室
http://sendai-banji.com/
・スケジュール:
14:00~14:05 研究代表者から挨拶
14:05~14:25 佐藤大介氏(宮城資料ネット)
「東日本大震災における歴史資料保全活動の現状と課題」(仮)
14:25~15:15 被災地各資料ネットよりの報告
15:15~15:35 松下正和氏(近大姫路大学)
「東日本大震災における歴史資料保全活動の現状と課題」
15:35~15:40 休憩
15:40~16:00 佐々木和子氏(神戸大学)
「震災資料の現状と課題」(仮)
16:00~16:20 添田仁氏(神戸大学)
「東日本大震災発生後の歴史文化に関する新聞報道と各種団体の動きについて」(仮)
16:20~16:35 多仁照廣氏(敦賀短期大学)
「水損文書の簡易脱水について」(仮)
16:35~16:45 内田俊秀氏(京都造形芸術大学)
「イタリア・ラックイラ市における2009年地震に対する文書館の活動」(仮)
16:45~16:50 休憩
16:50~17:30 討論
【11月27日(日)】
・被災地巡検
石巻日和山→津波被災本間家土蔵→塩竃神社→亀井邸(予定)
・主催:
科学研究費補助金基盤研究(S)
「大規模自然災害時の史料保全論を基礎とした地域歴史資料学の構築」
〔研究代表者:奥村弘〕研究グループ
| 2011.11.01更新 |
■DJIセミナー「チェルノブイリからの伝言―ヒト・放射能・資料―」
・日時:2011年11月18日(金)午後1時30分~
・場所:松本大学(会場は当日掲示)
松本市新村2095-1 松本電鉄上高地線「北新・松本大学前」すぐ。
駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。
入場無料(先着200名様。直接会場にお越しください。)
満席の場合は入場をお断りすることがあります。
◆プログラム
開会挨拶・趣旨説明 小川千代子氏(国際資料研究所)
第1部 ヒトと放射能
【基調講演】 菅谷昭氏(松本市長、医師)
「チェルノブイリ原発事故による放射能汚染の実態からフクシマは何を学ぶべきか」
第2部 放射能と資料
【主報告】上埜武夫氏(ウエノ・テクノリサーチ代表、元静岡大学教授)
「1992年開催のユネスコ・チェルノブイリ・アーカイブ専門家会議参加報告」
【関連報告1】
小川千代子氏(国際資料研究所)
「チェルノブイリで開発された放射能汚染文書の除染マニュアル」
【関連報告2】佐々木和子氏(神戸大学)
「記録を作り、記録を残す―次代へ伝える経験」
【質疑応答・意見交換】
◆詳しくは「国際資料研究所報 「DJIレポート」の電子版」 E-DJIReport」をご覧ください
http://djiarchiv.exblog.jp/16307805/
主催:国際資料研究所
共催:科学研究費補助金基盤研究(S)「大規模自然災害時の資料保全論を基礎とした
地域歴史資料学の構築」(研究代表者:神戸大学大学院人文学研究科 奥村弘)
松本大学
後援:松本市 BOSAIインターナショナル 日本アーカイブズ学会 ICA/SPA国際文書館
評議会/専門家団体部会 企業史料協議会 全国大学史資料協議会 全国歴史資料
保存利用機関連絡協議会
協賛:株式会社国際マイクロ写真工業社
| 2011.10.14更新 |
■第11回地域歴史資料学研究会(再)
(中止した9月21日の研究会を再度行います)
「震災資料の現状と課題」
・日時:2011年10月20日(木)10時00分~12時30分
・場所:神戸大学大学院人文学研究科A棟1F・学生ホール
・報告:
大場 利康氏 (国立国会図書館関西館)(予定)
「東日本大震災とデジタルアーカイブ」
佐々木和子氏(神戸大学地域連携推進室)
「阪神淡路大震災における震災資料」
板垣貴志氏(神戸大学大学院人文学研究科)
「神戸市震災関連行政文書の整理について」
【ご案内】
2011年3月11日に発生した東日本大震災は、被災地で人々の歴史や記憶にかかわるものを守ろうとする
さまざまな動きを呼び起こしました。直後の捜索活動にあたった自衛隊員が写真や位牌などを収拾したこと、
自治体職員が避難所で被災した写真を一つ一つ水できれいに洗い、乾かし、遺族に渡したという作業、
津波で土砂をかぶった地蔵を住民が掘りだし、それを高台に安置したこと。
また、被災した資料や文化財を救出する活動として、震災直後から各地史料ネット、saveMLAKなどが
展開しました。また、4月1日には文化庁の働きかけを契機に国立文化財機構はじめ幾多の文化財・
美術関係団体が被災文化財等救援委員会を立ち上げました。
これらの動きは、過去の記憶や歴史文化を伝える資料や文化財が、わたしたちの社会を形づくってきた
という意識に支えられたからこそ、起こったものです。震災にかかわるあらゆる資料を守りながら、
それを「震災資料」としてどのように伝え、生かしていくかもまた、大きな課題といえます。
今回の研究会では、東日本大震災をうけて、震災の記録や記憶にかかわる「震災資料」をめぐる今日的な
状況と問題を議論できればと考えています。みなさまのご参加をお待ちしております。
・主催:
科学研究費補助金基盤研究(S)
「大規模自然災害時の史料保全論を基礎とした地域歴史資料学の構築」
〔研究代表者:奥村弘〕研究グループ
・協力:
神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター
阪神・淡路大震災資料の保存・活用に関する研究会
| 2011.9.2更新、2011.9.21更新 |
| 2011.6.28更新 |
| 2011.2.9更新 |
| 2011.2.9更新 |
| 2011.2.9更新 |
| 2010.11.1更新 |
| 2010.11.1更新 |
| 2010.9.27更新 |
| 2010.7.5更新 |
| 2010.7.5更新 |
| 2010.7.5更新 |
| 2010.5.11更新 |