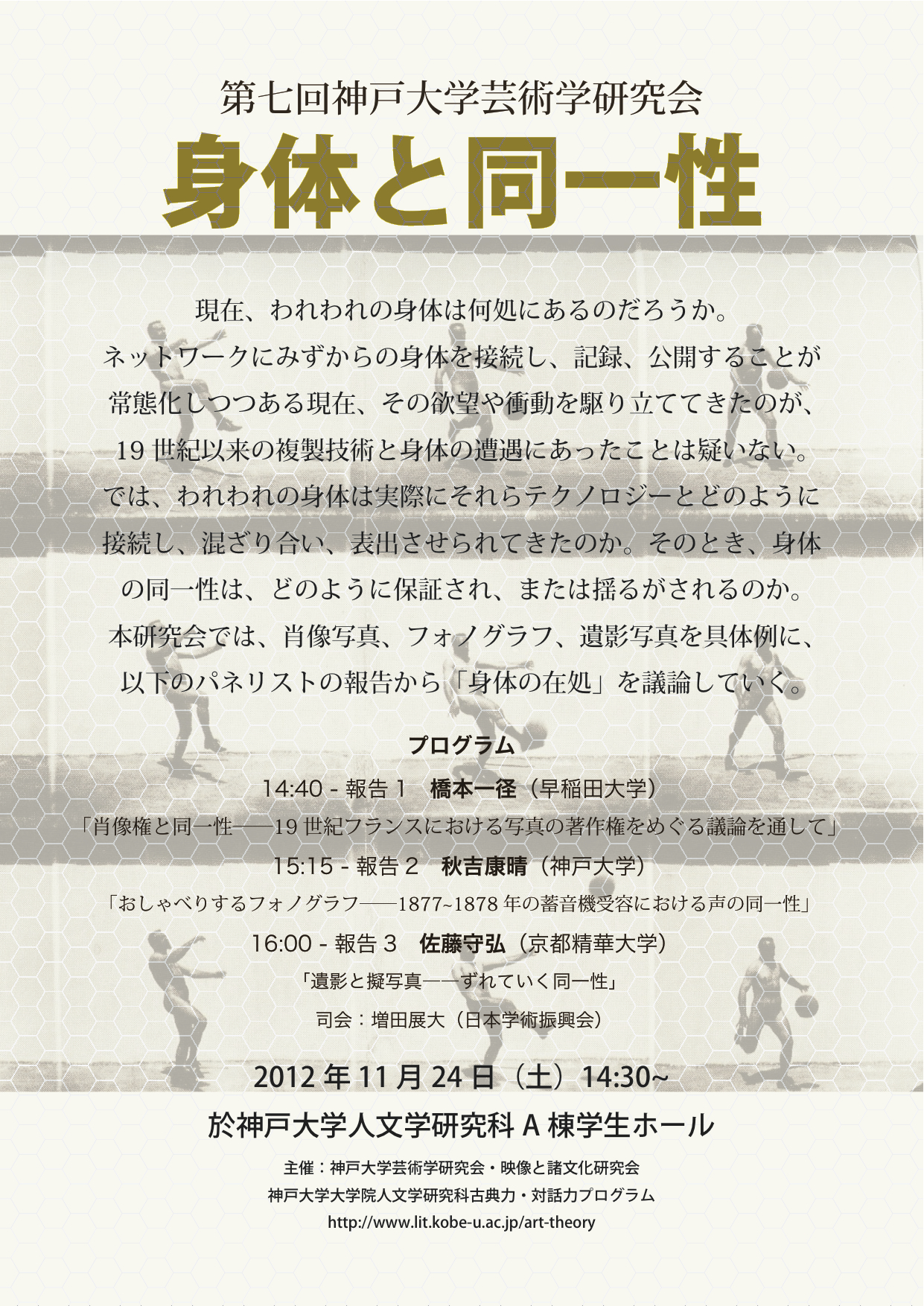第13回神戸大学芸術学研究会『コンタクト・ゾーンとしての身体ーーアメリカから考える』
2018.11.9up
日時・場所
佐藤良明(東京大学名誉教授)
グローバル化に伴い、国境の流動化が加速する現代の状況下で、異文化間の接触は活発化の一途を辿っている。この状況は移動による直接的な接触にとどまるものではない。テクノロジーの発展は、身体に直接間接に働きかけるメディアを作り出し、新たな仕方での他者との接触を可能にしている。「接触」の契機自体が、「他者との接触」という根源的な欲望を保持しつつ、さまざまに変奏され、多様化してきている。
そこで本研究会は、今日における身体と接触の美学を考えるにあたって、昨今の人類学で提唱される「コンタクト・ゾーン」という概念を掲げることを試みたい。コンタクト・ゾーンとは、異なる文化的背景を有する主体同士が非対称的な関係性を有しながら接触することで、相互に主体の変容が迫られる動態的な空間を指す。本研究会の意図は、空間的な意味合いの強かったコンタクト・ゾーンという概念を身体そのものにまで拡張し、身体を複数の接触の場として考えることにある。そこで問題となるのは、「接触」の諸相なのである。
こうした問題を考えるにあたって、本研究会は、それ自体コンタクト・ゾーンと呼ぶことのできるアメリカ合衆国の現代文学から音楽に至るまで、人種や文化の異種混淆性に目配せをしながら広範にアメリカ文化を研究する佐藤良明氏と、アメリカやフランス、ドイツなど複数の領域に渡る「接触」と近代性について考えを進めてきた高村峰生氏をお呼びし、接触、文化、芸術をめぐる根本的な問題について議論を深めたい。
そこで本研究会は、今日における身体と接触の美学を考えるにあたって、昨今の人類学で提唱される「コンタクト・ゾーン」という概念を掲げることを試みたい。コンタクト・ゾーンとは、異なる文化的背景を有する主体同士が非対称的な関係性を有しながら接触することで、相互に主体の変容が迫られる動態的な空間を指す。本研究会の意図は、空間的な意味合いの強かったコンタクト・ゾーンという概念を身体そのものにまで拡張し、身体を複数の接触の場として考えることにある。そこで問題となるのは、「接触」の諸相なのである。
こうした問題を考えるにあたって、本研究会は、それ自体コンタクト・ゾーンと呼ぶことのできるアメリカ合衆国の現代文学から音楽に至るまで、人種や文化の異種混淆性に目配せをしながら広範にアメリカ文化を研究する佐藤良明氏と、アメリカやフランス、ドイツなど複数の領域に渡る「接触」と近代性について考えを進めてきた高村峰生氏をお呼びし、接触、文化、芸術をめぐる根本的な問題について議論を深めたい。
プログラム
第一部 神戸大学芸術学研究室所属の院生による研究発表
(司会:大橋完太郎)
13:10- 西橋卓也(神戸大学人文学研究科博士課程)
13:50- 質疑応答
第二部 登壇者による研究報告
(司会:大橋完太郎、コメンテーター:前川修、西橋卓也)
14:10- 報告1 高村峰生氏(関西学院大学国際学部准教授)
14:50- 報告2 佐藤良明氏(東京大学名誉教授)
15:30- 休憩10分
15:40- 共同討議
(17:00終了予定)
発表要旨
西橋卓也「現代アメリカ映画におけるコンタクト・ゾーンの諸相――『クラッシュ』と『マインド・シューター』における接触の表象を通じて」
従来のコンタクト・ゾーン概念は、直接的/身体的な接触において生じる主体変容の場に焦点を当ててきた。こうしたコンタクト・ゾーンはグローバル化が進行し、デジタル技術が日常へとますます浸透していく現代においては、間接的/脱身体的な次元にまで拡張されていると言えるだろう。こうした現状を踏まえた上で、本発表では現代のアメリカ映画において人種間での「接触」がどのように表象されているのかを考えてみたい。発表では、ポール・ハギス監督『クラッシュ』(Crash, 2005)、アレックス・リベラ監督『マインド・シューター』(Sleep Dealer, 2008)の二作品を取り挙げる。『クラッシュ』は、ロサンゼルスを舞台に、交通事故をきっかけとした人種的な接触が身体的な次元で描かれるのに対し、『マインド・シューター』では、メキシコのティファナからアメリカの工事現場へと仮想空間を通じた接触が脱身体的な次元で描かれている。これら二作品の比較分析を通じて、現代アメリカ映画におけるコンタクト・ゾーンの諸相を明らかにする。
高村峰生「1920年代のホピとプエブロ――D. H. ロレンスとウィラ・キャザーの交差する時空間」
D. H. ロレンスとウィラ・キャザーは米国南西部の原住民への強い関心を共有しており、ロレンスのニューメキシコ州タオス滞在時の1925年にキャザーは彼と彼の妻フリーダを訪問している。本発表では、両作家の1924-25年におけるホピ族やプエブロ族との接触について事実を整理し、彼らがそれらをどのように捉え、記述したかを、主としてロレンスのエッセイ“The Hopi Snake Dance”(1924)とウィラ・キャザーの小説Death Comes for the Archbishop(1927)を比較しながら検討したい。1900年前後よりすでに観光の対象となっており、アビ・ヴァールブルクやカール・ユングも研究対象とした米国南西部原住民の儀式に、二人の作家はそれぞれ西洋的価値観を相対化する意義を見出していた。このことを、1924年に制定されたプエブロ土地法や1880年代以来進められていた原住民同化政策の進展、および伝統文化保護を訴えたインディアン局長官ジョン・コリアによる政策などの時代背景と関連付けながら論じ、コンタクト・ゾーンとしてのタオスについて考察してみたい。
問い合わせ;芸術学研究室 西橋卓也
nishi24841119(at)gmail.com(@に変えてください)