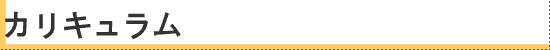
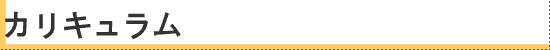
Last updated at 20 March. 2002
比較造形文化論
|
日本美術史の特質 |
百橋教授 |
火曜・3限 |
近代造形史論
|
宮下助教授 |
木曜・2限 |
|
博物館学A |
中村講師 |
水曜・4限 |
|
情報メディア活用論
|
嶋林講師 |
月曜・3限 |
|
美術史演習 |
百橋教授 |
火曜・2限 |
|
美術史演習 |
宮下助教授 |
木曜・3限 |
|
美術史演習 |
近隣美術館・文化財等の実地見学 |
百橋教授、宮下助教授 |
金曜・3限 |
| 美術史調査法 | 宮下助教授 | 金曜・4限 | |
| 日本・東洋美術史 (美術史特殊講義) (博物館実習AⅠ) |
若冲再考 | 佐藤講師 | 集中講義 (7/19~13) |
| 美術史特殊講義 (博物館学CⅠ) |
①西洋美術史方法論②図像学入門 ③フランス近代美術の特殊講義 |
木村講師 | 集中講義 |
日本・東洋美術史特殊研究 |
日本美術史の特質 |
百橋教授 |
火曜・3限 |
芸術史演習 |
アジアの中の日本美術史 |
百橋教授 |
水曜・2限 |
西洋美術史特殊研究 |
宮下助教授 |
木曜・2限 |
|
芸術史演習 |
宮下助教授 |
木曜・4限 |
| 西洋美術史特殊研究 | ①西洋美術史方法論②図像学入門 ③フランス近代美術の特殊講義 |
木村講師 | 集中講義 |
日本絵画論
|
作品と史料の調査研究
|
百橋教授 |
水曜・1限 |
西洋美術論
|
美術作品の調査研究及び美術史上の諸問題の検討 |
宮下助教授 |
木曜・2限 |
アジア美術論 |
正倉院宝物にみる8世紀の東アジア美術の影響 |
三宅講師 |
|
日本美術史
|
平安時代仏教美術に焦点を合わせ、和様化の過程を実証的に研究する。 |
百橋教授 |
火曜・3限 |
美術史概論
|
美術史学の基礎的方法論・実践を学ぶ。イタリア美術を例に取り上げる。 |
宮下助教授 |
木曜・2限 |
博物館学B |
学芸員業務のうち、展覧会開催までの実際を解き明かす。 |
石川講師 |
集中講義
|
情報メディア活用論
|
情報化の歴史を辿りながら、メディアの教育への応用・問題・法律・整理法などを講義。 | 大塚講師、鈴木講師、松尾講師、服部講師、水口講師 |
金曜・4限 |
アジア美術史演習
|
唐代から宋代にかけての美術に関する文献と実際の作品を比較検討。 |
百橋教授 |
火曜・2限 |
西洋美術史演習
|
美術史の基礎的文献の講読。または各自興味のある美術作品・作者についての調査・発表。 |
宮下助教授 |
木曜・3限 |
文化資源学
|
文化財としての美術作品の保存と活用の実態を美術館や社寺の見学を通して把握。 |
百橋教授、宮下助教授 |
金曜・3限 |
| 美術史資料演習 (美術史演習) |
美術作品及び資料の調査法の演習。美術館や社寺での教官・学芸員の説明を聞きながら作品の見方を学ぶ。 | 宮下助教授 | 金曜・4限 |
| 日本美術史演習 (美術史演習) (博物館実習A) |
画家酒井抱一について、様々な角度から検討を加える。 | 影山教授 (国際文化学部) |
水曜・3限 |
| 美術史特殊講義 (博物館学CⅠ) |
ピカソをめぐる複数の視点について論じる。 | 太田講師 | 集中講義 |
日本・東洋美術史特殊研究 |
平安時代仏教美術に焦点を合わせ、和様化の過程を実証的に研究する。 |
百橋教授 |
火曜・3限 |
芸術史演習 |
歴代名画記等の文献と実際の作品との比較検討から、唐宋美術の本質に迫る。 |
百橋教授 |
水曜・2限 |
西洋美術史特殊研究 |
美術史学の基礎的方法論・実践を学ぶ。イタリア美術を例に取り上げる。 |
宮下助教授 |
木曜・2限 |
芸術史演習 |
美術史の専門的・重要な外国語文献の講読、討議。各院生の研究分野についての研究発表。 |
宮下助教授 |
木曜・4限 |
| 西洋美術史特殊研究 | ピカソをめぐる複数の視点について論じる。 | 太田講師 | 集中講義 |
日本絵画論
|
作品と史料の調査研究
|
百橋教授 |
水曜・1限 |
西洋美術論
|
美術作品の調査研究及び美術史上の諸問題の検討 |
宮下助教授 |
木曜・2限 |
アジア美術論 |
正倉院宝物にみる8世紀の東アジア美術の影響 |
三宅講師 |
|
![]() 過去のカリキュラム
過去のカリキュラム